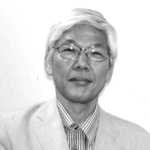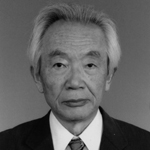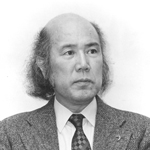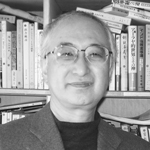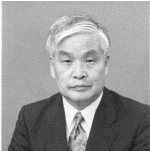|
| |
|
|
|
| |
| 岩崎武夫(いわさき たけお) |
| |
 |
|
1925年、東京生まれ。1959年、法政大学文学部大学院終了。元千葉経済大学教授。法政大学講師、東京医科歯科大学教養部教授、千葉経済大学教授を歴任の後、2000年、同大学定年退官。
研究テーマは、日本の中世・近世の語り物文芸。著書に、 『さんせう太夫考』、『続さんせう太夫考』など。 |
| |
|
|
| |
| 大隅和雄(おおすみ かずお) |
| |
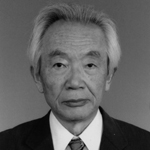 |
|
1932年、福岡県生まれ。1964年3月 東京大学大学院博士課程単位修得退学。1964年4月 北海道大学文学部(助教授)。1977年4月 東京女子大学史学科(教授)。現在、東京女子大学名誉教授。著書に、日本思想大系 19 『中世神道論』 、 『愚管抄を読む』 、『中世思想史への構想』 、『中世 歴史と文学のあいだ』、『日本の文化をよみなおす: 仏教・年中行事・文学の中世』など。 |
| |
|
|
| |
| |
| 大津雄一(おおつ ゆういち) |
| |
 |
|
1954年、神奈川県生まれ。1977年、早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。1988年、早稲田大学大学院文学研究科博士課程後期課程退学。博士(文学)。現在早稲田大学大学教育・総合科学学術院教授。著書に、『北条五代記』、『新編日本古典文学全集 曾我物語』、『声の力と国語教育』(以上、共著)、『軍記と王権のイデオロギー』など。
|
| |
| |
|
|
| |
|
|
| |
| 甲木惠都子(かつき えつこ) |
| |
 |
|
1934年、東京生まれ。牛込加賀町で、文部官僚から自民党代議士に転じた故・甲木保氏の長女として生まれまれる。郡上紬の宗廣力三氏に師事。手紬糸を天然の植物で染め、手機で織るという、土の香りのする紬織からはじめ、各地の絣を研究。1965年、岐阜県郡上郡八幡町郡上工芸研究所入門。1971年、第8回伝統工芸日本染織展入選。文化庁長官賞受賞。第1回個展(東京・日本橋三越)。1972年、第9回伝統工芸日本染織展。文化庁長官賞受賞。1973年、第10回伝統工芸日本染織招待出品。1974年、第20回伝統工芸展入選。1975年、パリ・サントノーレにて個展。1977年、第9回第三文明展推薦作家となる。1979年、第16回伝統工芸日本染織展鑑審査員。資生まれ堂画廊(東京)にて個展。1981年、銀座ポーラ画廊にて個展。1984年、西部工芸展出展。ガーデンパレス(福岡)にて染織展。1985年、天神ギャラリー(福岡)にて無地・帯作品展。銀座ラ・ポーラ(東京)にて染織展。2007年、日本橋高島屋(東京)にて、「『平家物語』を織る」展。2008年、矢代仁にて『おくのほそ道』展。日本工芸会正会員。 |
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 小松茂美(こまつ しげみ) |
| |
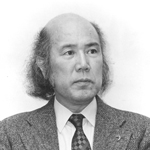 |
|
1925年、山口県生まれ。1959年、山口県立柳井中学校卒業。鉄道省に入り、柳井駅に勤務。1945年、広島で被爆。「平家納経」に魅せられ、学問の道に進む。東京国立博物館美術課長を経て、現在、センチュリー文化財団理事・館長。博士(文学)。柳井市名誉市民。『平安朝伝来の白氏文集と三蹟の研究』により日本学士院賞。「『平家納経の研究』の完成を含む古筆学研究体系化の業績」により朝日賞受賞。著書に、『後撰和歌集・校本と研究』をはじめ『日本絵巻大成』(正・続・続々)(全54巻)、『古筆学大成』(全30巻)、『小松茂美著作集』(全33巻)など。
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 五味文彦(ごみ ふみひこ) |
| |
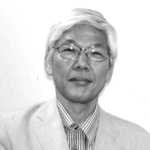 |
|
1946年、山梨県生まれ。1968年、東京大学文学部国史学科卒業。1970年、東京大学大学院修士課程終了。神戸大学、お茶の水女子大学、東京大学教授を経て、現在放送大学教授、東京大学名誉教授。著書に、『吾妻鏡の方法』、『中世のことばと絵』、『藤原定家の時代』、編著に『現代語訳 吾妻鏡』(全16巻)、全集『日本の歴史』(全16巻)など。
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 薦田治子(こもだ はるこ) |
| |
 |
|
1950年、東京生まれ。1973年東京芸術大学音楽学部楽理科卒業。1981年同
大学院音楽研究科博士課程後期満期退学。2003年お茶の水女子大学より学位
(人文)を取得。同大学の助教授を経て、現在武蔵野音楽大学教授。専門は日本
音楽史。平家(琵琶)、語り物の音楽研究、琵琶をおもな研究領域とする。
編著
書に『日本の語り物:口頭性・構造・意義』(共編)、『平家の音楽 - 当道の伝
統』(単著)、『あなたが読む平家物語』『岩波講座日本の音楽・アジアの音楽』
『日本の楽器 - 新しい楽器学へ向けて』(以上共著)などがある。
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 末木文美士(すえき ふみひこ) |
| |
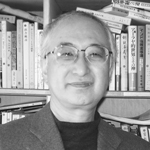 |
|
1949年、山梨県甲府市生まれ。仏教学者。専攻は仏教学、日本宗教史。1973年、東京大学文学部印度哲学専修課程卒業。1975年、同大学院人文科学研究科修士課程修了。1978年、同博士課程単位取得退学、1995年、東京大学文学部教授。現在、同大学院人文社会系研究科教授。博士(文学)。東京大学 大学院人文社会系研究科 思想文化学科 教授(研究分野:印度哲学・仏教学 、宗教学 、思想史)。
著書に、『仏教 - 言葉の思想史』、『解体する言葉と世界』、『「碧巌録」を読む』、『日本仏教思想史論考』、『鎌倉仏教形成論』、『日本仏教史』、『日蓮入門』、『明治思想家論 近代日本の思想・再考I』、『近代日本と仏教 近代日本の思想・再考II』、『仏教vs.倫理』、『日本宗教史』、『思想としての仏教入門』。編集・編著書に、『岩波仏教辞典 第二版』、『岩波哲学・思想事典』がある。 |
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 杉本圭三郎(すぎもと けいざぶろう) |
| |
 |
|
1927年、東京生まれ。1959年、法政大学大学院日本文学修士課程終了。
現在法政大学名誉教授。
著書に、論文「太平記論」(『文学』1959年8月)、論文「平家物語の変貌」(『文学』1968年10月)。共著に『シンポジウム日本の文学「平家物語」』。個人全訳注の『全訳注平家物語』(全12巻)など。
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 利根川清(とねがわ きよし) |
| |
 |
|
1957年栃木県足利市生。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。1998年早稲田大学大学院教育学研究科後期博士課程退学。現在早稲田大学高等学院教諭。
論文「『義経記』の笑い」、「『義経記』今何が問題か」、「『海道記』の歴史性」など、中世軍記を中心に、テキストと芸能・民俗の両面から研究を進めている。 |
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 三木紀人(みき すみと) |
| |
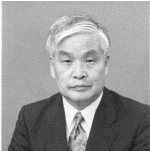 |
|
1935年、兵庫県姫路市生まれ。1959年、東京大学文学部国文科卒業。1966年、同大学院人文科学研究科国語国文学博士課程単位取得満期退学。1971年、成蹊大学文学部助教授。1975年、お茶の水女子大学文教育学部助教授。1980年、同教授。2001年、同大学定年退官。現在、お茶の水女子大学名誉教授。同年、城西国際大学人文学部教授。日本研究センター所長。2002〜3年、同学部国際文化学科長。2004年、同学部長、人文科学研究科長。2006年、研究テーマは、中世日本の知識人の文学、特に随筆・説話。著書・論文に、 『方丈記・発心集』、『徒然草全訳注』、『多武峰ひじり譚』、『日本周遊古典の旅』、『鴨長明』など。 |
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| 山下宏明(やました ひろあき) |
| |
 |
|
1931年、兵庫県生。1958年、神戸大学文学部卒業。1964年、東京大学大学院人文科学研究科国語国文学専攻博士課程終了。博士(文学)。名古屋大学、愛知淑徳大学教授を経て、現在名古屋大学名誉教授。
著書に、『平家物語研究序説』、『平家物語の生成』、『太平記』、『語りとしての平家物語』、『琵琶法師の「平家物語」と能』。校注に新日本古典文学大系『平家物語』(上)(下)(梶原正昭と共著)など。
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|